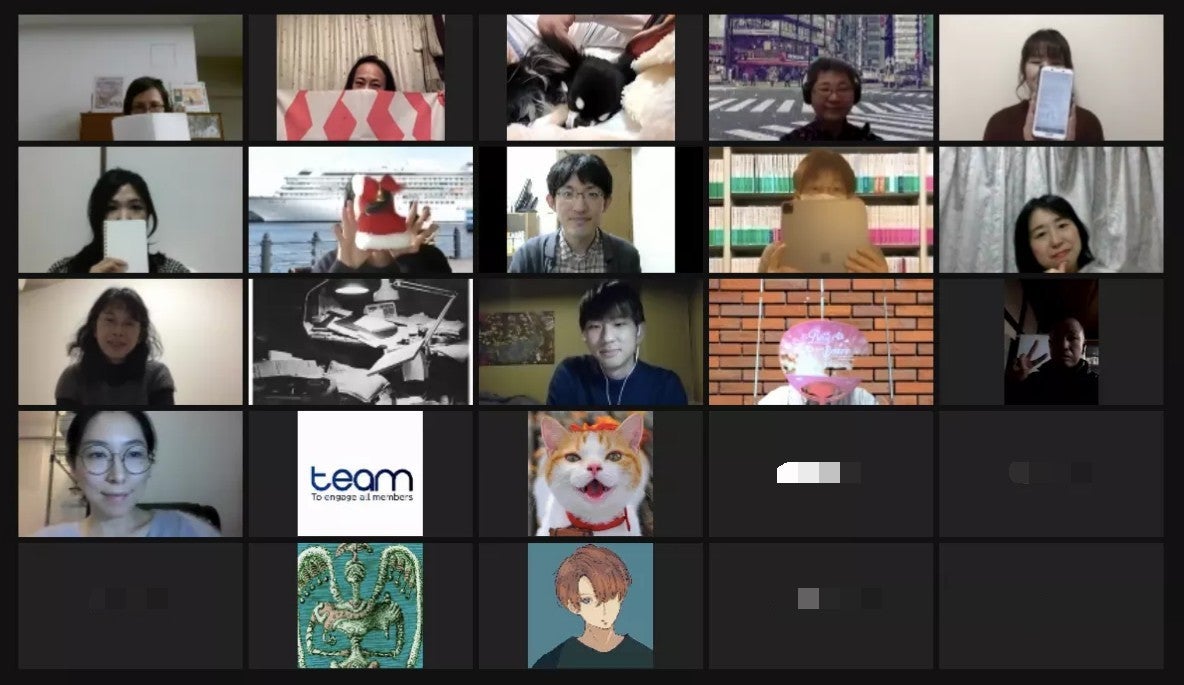そう問われているような読書会だった。
翻訳家の柴田元幸さんをゲストに迎えた、クリスマス読書会&トークショー。
海外文学好きであればその名を知らぬ人はほとんどないであろう柴田元幸さんがゲストとあって、読書会は72名、トークショーは98名と多くの参加者が集まった。
(※トークショーは12月11日の事前読書会または今回の読書会どちらかに参加した人が参加可能)
今回の読書会は柴田さんが選書した課題の短編二作品を読み、どちらが好きかを話し合うというもの。
課題作品は申込みの時点では明かされておらず、参加者だけが知ることができるという、まさにクリスマスプレゼントのような仕掛け!
さてプレゼントの箱の中から出てきたのは、ポール・オースター『オーギー・レンのクリスマスストーリー』と、ウィリアム・バロウズ『ジャンキーのクリスマス』の二作品。
どちらも短めのクリスマスのお話だけれど、よくある心温まる物語…では済まない様子。
読書会が楽しみになってきた!
さあ読書会が始まり、どちらの作品が好きか、それはなぜなのかと語り始めると、あら不思議。自己紹介以上に自己紹介となる、その人の人となりが見えてくる。
感激屋、ひねくれ者、現実主義者…読み手によってまるでリトマス試験紙のように色が変わる二つの物語。
読書会の途中で柴田さんがそれぞれのグループを回り、どちらが好きかを聞いたところ、性別や年齢に偏りなくほぼ半々に分かれたようだった、とのこと。
ただ、同じ「好き」でも理由はさまざま。
もちろん、反対にここが「嫌い」という意見も出る。
読書会である参加者が「『オーギー・レン』の方は、所詮オーギーの作り話。そんなものを聞いて意味があるのかな」と言ったことにハッとした。
作り話と言ってしまえば小説自体がそもそも虚構。
なぜわたしたちはあえて「作られた」物語を読むのだろうか。
今回の読書会ではまさにその意味を問われた気がした。
物語という鏡を通してわたしたちは自分の顔を覗き込んだり、他人の顔を映してみたりしているのかもしれない。
そうする中で、いつもと違う角度から自分や他人のことを見て、新たな発見をする。
作られたものだからこそのバリエーションの多さでさまざまな可能性を見せてくれるのは、物語の魅力の一つだと思う。
続くトークショーでは、「いわゆる“クリスマスストーリー”は心温まる話ばかりなのか?」という参加者からの質問に対し、課題作品とはまた違ったテイストの短めのクリスマスストーリーをいくつか朗読してくださった。
(わたし自身は正直課題作品よりも朗読してくれた作品の方が好きだった)
その他にも続々と質問が寄せられる中、一つ一つにまじめに答える柴田さんの様子からは文学への温かな愛情が感じられ、「こんな人が訳している作品なら、もっと読んでみたいな」と思った。
読書会・トークショー合わせて約3時間半と長めの開催時間ではあったが、文学の魅力、読書会の魅力、柴田元幸さんの魅力…といろいろな魅力を堪能できた濃い時間だった。
読書会に参加された方、柴田さん、ありがとうございました!