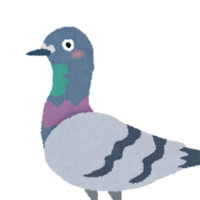駒井組の課題本、リュドミラ・ウリツカヤ『ソーネチカ』の読書会は、もともと好きだったロシア文学の良さを120%感じられる充実した会でした。私が初読した時、「これは名付けられない、取るに足らないと思われがちな才能を持った女性の話だ」と感じ、自分の人生観にも深く突き刺さる物語として受け取りました。
読書会での深堀り、駒井さんの解説、自分で考えた他の作品との共通点など、をそれぞれ書いてみたいと思います。話が長くなりますので①~⑥の気になる所だけでも読んでいただければと思います。
目次
①ソーネチカは受動的に見えて相当頑固者?
②ソーネチカに授けられた「名づけられない」才能
③ロシア文芸等に見られる「聖なる愚か者」
④古典のような作品だがシスターフッドの描写も見いだせる
⑤意外と文学・映画にある「勝手に幸せになる女性主人公の系譜」
⑥「閉じた主観的幸せ」と無視できない「外の世界」
①受動的に見えて相当頑固者?
『ソーネチカ』はユダヤ系のパッとしない女性、ソーネチカの幼少期から晩年までの人生をコンパクトにまとめた中編です。読書が大好き、でも地味系のソーネチカは図書館で働きながら唐突に人生の伴侶となる男性と出会い、子育てをするというごく平凡な毎日を送っていましたが、中年になったころ夫の不倫・死亡騒動に巻き込まれます。
ドストエフスキー作品みたいなロシア文学だったらこの不倫騒動の愛憎やもめごとで上下巻は余裕ですが、ソーネチカは夫の裏切り不倫相手だったわが子同然の孤児の少女も許し、受け入れます。そして「自分は幸福だ」と納得し、寂しく孤独な晩年を迎えても「一人で本が読めてこんな幸せなことはない」と思うのです。
彼女は怒るべき所で怒らず、流されるままに生きている女性ではないのか?と初見では思うかもしれませんが、よくよくソーネチカの描写を追っていくと、彼女が相当頑固に自分の「幸せ」を手元に残そうとしていることが分かりました。
読書会でも指摘がありましたが、ソーネチカは同情に流されてもいい場面であえて客観的には苦しい選択をしています。
・優しい両親の申し出を断って反体制の芸術家の夫と流刑地に行き、そこで出産する
・やめておけばいいのに娘の友達の孤児を愛してしまい、そのまま引き取る
・周りの同情を振り切って夫の不倫相手の孤児を庇護する
・周りの援助を断りあえて質素な部屋で一人暮らしの晩年を選ぶ
これは、彼女が無欲だから、善人だからという見方もできます。しかし、じつは客観的幸福を度外視して自分が信じる主観的幸せを追求した結果、なのではと思いました。周りの善意とか同情による援助も断ってその道を選んでいるので、流されているように見えて実際のところかなり頑固だとも思えます。
読書会で指摘があったのですが、ソーネチカはドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』のアレクセイ・カラマーゾフの象徴的な台詞「君の人生は不幸なものになるでしょう(中略)ただし全体としては祝福しなさいよ」を地でいくタイプであり、不幸になるような道をえらんだとしても、全体として自分の人生を祝福してしまう人間でした。
②ソーネチカに授けられた名づけられない才能
自分の眼前にある状況や人を愛して「なんて幸せなんだろう」と勝手に幸せになれるのは相当に稀有な才能だと思います。ソーネチカの「文学を愛し耽溺できる」という性質も、誰かの助けを借りず自力で至福の瞬間を作り出せるという意味では彼女の「主観的に幸せになれる才能」の一部であると言えるでしょう。
ソーネチカの身近なものを愛せる才能や読書で自力救済的に幸せになれる才能というのは、彼女の夫ロベルトの芸術的才能のように、誰かに評価されたり、体系づけられたりする類のものではありません。この『ソーネチカ』という物語を読んだ読者は、これが相当にな強度を持った才能と分かります。しかし、おそらく世間的には「従順な性格」「女子供の取るに足らない読書趣味」としか分類されてこなかった質の才能なのだと思います。
彼女の特異な才能は、世間的には名付けられない類のもので、何の権威もありませんが、『ソーネチカ』という物語を読んだ読者はこの異様な才能に驚嘆するし、「聖性」としかいえないものの片鱗を感じることができたのではないでしょうか。
私が『ソーネチカ』を読んで連想したのは、ラース・フォン・トリア―監督、ビョーク主演の『ダンサー・イン・ザ・ダーク』です。この作品の主人公セルマはミュージカルをこよなく愛しており、自分の解雇や失明、無実の罪の刑死を前にしてもミュージカルの世界に入り込むことで、幸福を感じます。それは一見現実逃避のようにも見えますが、彼女が音楽を愛し、ミュージカルに入り込んでいく様子が映画の中では実際のミュージカルシーンとして描かれます。それは完全に彼女の主観の世界であり、現実の人間たちはその幸福な夢を一緒に見ることはできないのです。
ソーネチカは作中何度も「こんな幸せで良いのかしら」と口にしますが、彼女の主観的幸せというのもこの『ダンサー・イン・ザ・ダーク』にあった夢想のミュージカルのようなものだと感じました。読者は決して一緒に共有することができない、彼女の中だけにあり、彼女だけが感じ取れる至上の幸福があえて詳細な描写を省いて描かれているのだと思います。
駒井さんの解説では、フランス文学のようにあえて心情を細かく書かず、行動で示すのがロシア文学の特徴でありウリツカヤの持ち味であるとありました。このテクニックはソーネチカのような「主観的幸福の世界」を持っている人の表現としては適切だったと感じます。
ソーネチカの感じる幸福さを読者は一緒に感じることはできないが、彼女はその幸福に満足しており、それは間違いなく幸福である。そして読者はその見えない幸福の存在を信じることしか許されていないという距離感。これは柴田元幸先生が短評に載せていた言葉そのものだったと思います。
この小説の主人公は不思議な人である。見るからに幸せそうなときに「なんて幸せなんだろう」と考えるのはともかく、親しい人に裏切られ、失望させられて、たいていの人間なら激怒し絶望しそうなときでも、何か悦ぶべきことを見つけて、やはり「なんて幸せなんだろう」と考えている。そんな彼女に、作者は無垢ゆえの神々しさを見ているのだろうか。たぶんそうではあるまい。とにかくそういう人が作者の頭から生まれてしまったのであり、そうやって生まれた人を、作者はただそういう人として描いた。人間を祝福する上で、これ以上正しいやり方があるだろうか。
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』では、主人公の客観的様子は味気ない手持ちカメラのドキュメンタリー調で撮られていますが、夢想のミュージカルは100台以上のカメラを使った美しい光景として撮影されています。ソーネチカの客観的行動と、彼女の心の中の幸せもそういうものなのではないか…。私たちが見ることができないだけで、彼女が感じる幸せとはとても一人では抱えきれないほど豊かで美しい世界なのではないか…。という感想を持ちました。
③ロシア文芸等に見られる「聖なる愚か者」
駒井さんの解説にもありましたが、ソーネチカの何でも許してしまう、異様とも言えるほど潔い性格はロシア文芸ではよく見るタイプの「理想的人間」だと思いました。特に良く似ていると思ったのがドストエフスキーの『白痴』の主人公ムイシュキンです。彼も異様に気前がいい人間であり、『ソーネチカ』であったような男女の三角関係にあっても、相手の幸福のために恋敵が結ばれることを願う「周りが引くレベルの善人」として描かれています。
異様に善性が高いムイシュキンですが、周りの人間とはあまりにちがうのでその善意は一種の狂気のようにも描かれています。聖人というのはお花畑で優しいだけの人ではなく、恐ろしい狂人、あるいは手におえない愚か者と紙一重でもあるんですね…。
また、芥川賞作家で『白痴』オマージュの長編小説を書いている鹿島田真希もドストエフスキーを意識して自分の作品にそういった「聖なる愚か者」という存在を登場させています。「聖なる愚か者」とは一見損してばかりでその善意は滑稽でもある不器用な人間です。芥川賞受賞作の『冥途めぐり』では、こういう台詞が出てきます。
この人は特別な人なんだ。奈津子は太一を見て思った。今まで見ることのなかった、生まれて始めて見た、特別な人間。
ただとても大切なものを拾ったことだけはわかる。それは一時のあずかりものであり、時が来ればまた返すものなのだ。
別作品ではありますが、ロシア文芸の「理想的人物」やソーネチカの思考回路を理解するのに、このセリフが補助線になると思います。ソーネチカは自分の夫や娘や築いてきた生活すべてを「自分はこの幸せを一時与えられているだけなのではないか」と感じていますが、それは、彼女が目前にある者をすべて「恩寵」として受け取ってきたからではないでしょうか。
夫の不倫、裏切りに執着しなかったのも、ソーネチカが配偶者との関係や妻としての地位などの理屈を度外視した「目の前のものを恩寵として捉える主観」を基盤に置いていたからだと考えられます。
ソーネチカ自身はユダヤ教の熱心な信者ではなかったようですが、ロベルトのような近代的自我を持った人間とは異なる、「神からの贈り物と共に生きる」世界観で生きていたことが読み取れました。
④古典のような作品だがシスターフッドの描写も見いだせる
ソーネチカの造形は19世紀以来のロシア小説の系譜の1つですが、ウリツカヤは現代の女性作家らしく、シスターフッドとも解釈できる要素を本作に入れ込んでいます。母ソーネチカ、ちょっとアホっぽい問題児のターニャ、孤児の美少女ヤーシャの3人はヤーシャとロベルトの不倫というトラブルの渦中にあっても、お互いに憎み合ってはいません。
これが普通の作品だったら男をめぐって女たちが血みどろの争いを繰り広げたりするのですが、本作はものすごく淡々としています。ソーネチカは嫉妬よりもヤーシャへの同情心と愛着が上回って庇護するし、ヤーシャもソーネチカをバカにするのではなく母のように頼るので、男性への愛憎より女同士の愛着が勝るという結果に。
最近読んだミソジニーに関する記事によると、「男性に選ばれること」を優先する価値観だと、女同士の争いや分断が起きるそうです。それを踏まえると、ソーネチカとヤーシャはそういう「男性を中心とする人間関係」の枠外で絆をはぐくんでいましたし、お互いがお互いとして特別な人間関係であったと言えそうです。
また、ヤーシャはターニャを利用していはいるのですが、なんだかんだでターニャはヤーシャのおかげで自我に目覚めています。不倫トラブルを引き起こしても女三人に関してはそれぞれが与え・与えられるというシスターフッド的な関係性を維持していました。ここはウリツカヤもかなり気を使って描写していたように感じました。
参考:
⑤意外と文学・映画にある「勝手に幸せになる女性主人公の系譜」
『ソーネチカ』は読者を置いて主人公が主観的に幸せになる話、だと思いましたが、そういった主人公は他の作品にもいます。前述した『ダンサー・イン・ザ・ダーク』のセルマもそうですが、シャーリィ・ジャクスン『ずっとお城で暮らしてる』の主人公メリキャットもそういうキャラクターだと思います。(『ずっとお城で暮らしてる』は外の世界と違う精神性を持った少女が、姉を巻き込んで閉じた屋敷の中で勝手に幸せになる話)
しかし、『ソーネチカ』をふくめ、作品の視点というのは実はそれぞれ違っています。
『ダンサー・イン・ザ・ダーク」
悲劇:主人公が酷い目に遭うが主観的には幸せ、悲劇の善人として描かれる
『ずっとお城で暮らしてる』
ホラー:起きてることは陰鬱だが主観的には幸せ。主人公は魔女のような不吉な人間として描かれる
『ソーネチカ』
人間ドラマ:トラブルが深刻だが、主観的には幸せ。主人公は平凡な女性として描かれる
「勝手に主観的に幸せになる主人公」はその存在が特異なので、作品の語り口によって物語の様相が変わってくるのだと思います。幸せの基準が本人の中にあるので、その周りとのギャップの描き方によっては悲劇にもホラーにもコメディにもできそうですが、『ソーネチカ』はあえて一人の女性の一生という淡々とした人間ドラマにしている所に大きな個性があるのだと思います。
何の変哲もない(不倫トラブルはあったが)人生でも、このように特異な思考回路、精神世界で生きることは可能だ、そういう女性たちもこれまで現実にいたのではないかと思わせてくれるからです。
⑥「閉じた主観的幸せ」と無視できない「外の世界」
最後に、読書会でも出た「閉じた幸せ」に感じる危うさの話を少ししたいと思います。
読書会では、この受動的と思える人生の中でも幸せになれるソーネチカは『この世界の片隅に』のすずさんのような人ではないか、という指摘がありました。すずさんも大変な日常を幸せに感じる才能がありましたが、物語の最後ではその幸せは他の国の人々を踏みつけて得ていたものだったと悟ります。幸せの外に自分が加害者たりうる世界があったことを知るのです。
この『ソーネチカ』という物語はロシアでも人気があると言います。閉じた主観的世界で勤勉に、幸福に生きる模範的女性の物語としても読めますが、やはり「特別に人生を愛する才能を持った女性」の話として見たほうが良いかもしれないと感じました。ソーネチカのように本の世界に入り込みたい、と願う気持ちはありますが、彼女のような無尽蔵な許しと受け入れの力を普通の人間は手に入れることはできません。
それに、「この状況はおかしいのではないか」という疑いの視点を持たずいると、「耐える、受け入れ、許す」という美徳を悪人や国家に利用され、大きな流れに動員される恐れがあるからです。
それは、現在起きている侵略についても連想できるかなと思いました。欧米や日本がロシアに行っている経済制裁について「大祖国戦争を乗り切ったロシア国民なら耐えられる」というメンタリティがロシア人に少なからずある、という専門家の指摘を聞いたことがあります。
ソーネチカが持つような「耐える、受け入れ、許す」という美徳は一人の特異な女性の物語の中では美しくもありますが、それが「大きな物語」として動員された場合、現状を認識できなくなる危険をはらむと思います。
『ソーネチカ』はさまざまな作品やロシア文芸、思想とも関連付けて考えられる作品です。が、やはり、この美しい作品を一人の女性の新雪のように希少な人生の物語として大切に受容していきたいと感じました。