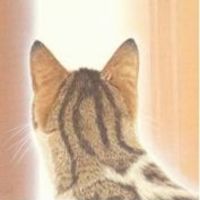
2021/03/03 20:04
3/2 フィロソフィア『ディスタンクシオン講義』
『講義』はエッセンスが分かりやすい良書でした!
というか原著の言葉遣いが難し過ぎ!
『講義』には原著から多くの文章が引用されていましたが、この難解な文章を見た上で、それでもなお原著に挑んでいる方々が多いのがさすが猫町ですね。心から尊敬します。
さて、まず個人的には意外だったのが、待合室でも読書会でも、趣味を分類して当てはめるという『ディスタンクシオン』の方針に反発する人が結構いるんだなということでした。
「好きで楽しんでいるものを分類されるなんて気に食わない。何をしたいのか分からない」という感じで。
個人的には、「社会学ってこういうもんだよね。どういう切り口で攻めてくるかな?」と平静心で読了してしまいましたが、読書会で話している内にブルデューはこの本で読者にむしろ反発させて批判させて議論を闘わせるように仕向けているんじゃなかろうか? 自分の読み方は邪道だったのでは?と、思うようになりました。
ただ、個人的にブルデューは「庶民的な趣味」と「正統的な趣味」はどちらかが優れているというわけではなく、それぞれ良いということで公平に扱っているように思いました。この姿勢はすごく好感。
個人個人が感じる幸福については触れられていない、という指摘もあり、ブルデュー自身が社会的に高い身分になっても庶民に寄り添おうとした「『怒りの才能』を生涯失わなかった『行動する知識人』」ということがここに表れている気がしました。
また、読書会では40年前には無かったインターネットの影響という話題も出ました。
誰でも情報にアクセスできるようになったから、階級はフラットになっていくんじゃないか?という意見もありましたが、個人的にはむしろ格差が広がるんじゃないかという考え。
いくら情報がネット上にあっても、そこにアクセスしようと思うハビトゥスを所持していないと存在していないのと同義ではないかと。
もちろん意欲がある人には機会が与えられる良い環境ではあると思うので、まずは自分が構造的な環境に囚われていることを自覚し、その上で飛び越えようと思うようになるかだと思います。
あと、個人的にオンラインオペラ会のサポーターをしている身としては、正統文化の大衆化についてはすごく気になりました。
原著では、「正統的文化と中間文化を混同させる狙いで作られる文化的生産物」として、演劇・文学の古典作品の「脚色」による映画化、クラシック音楽の「大衆的」な「アレンジ」または大衆歌曲のクラシック風「管弦楽用編曲」が挙げられていますが、現代だと「Youtubeでオペラを観る」のもここに入るんじゃないかと。
生舞台で生演奏で観る“本当の”オペラではなく、パソコンの画面上だけで「正統的文化」を味わっていると勘違いさせるという意味で。
もちろん、オペラに興味を持った人が気軽に演奏に触れることができるYoutubeってなんて素晴らしい!と思っていますので誤解の無きよう。(じゃないとオンラインオペラ会の意義が無くなる!)
ただ、混同するのではなくそれぞれ別物だと分かった上で、Youtubeと生演奏のそれぞれの楽しみ方を享受して欲しいなとは思います。
(※この辺りは、音楽学者の岡田暁生さんがコロナ禍の自粛下での音楽聴取について書いた『音楽の危機』で強く述べていることでもあります)
最後に、この本はどんなハビトゥスを持つメンバーがテーブルに集まるかによって話題が色々な方に転がる読書会向きの本だなと思いました。
何だかんだで原著は40年以上読まれているわけですし、やはり名著。
