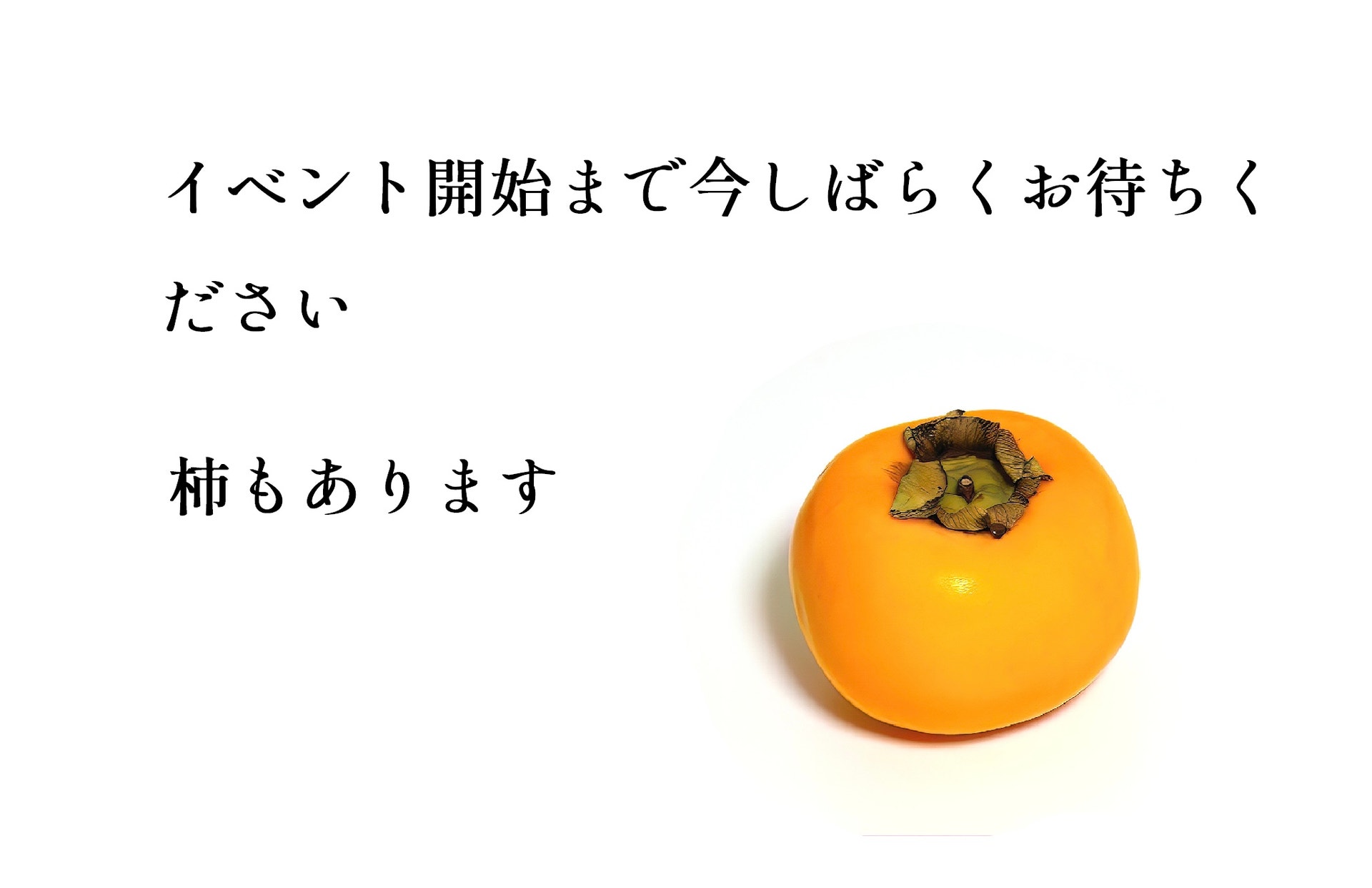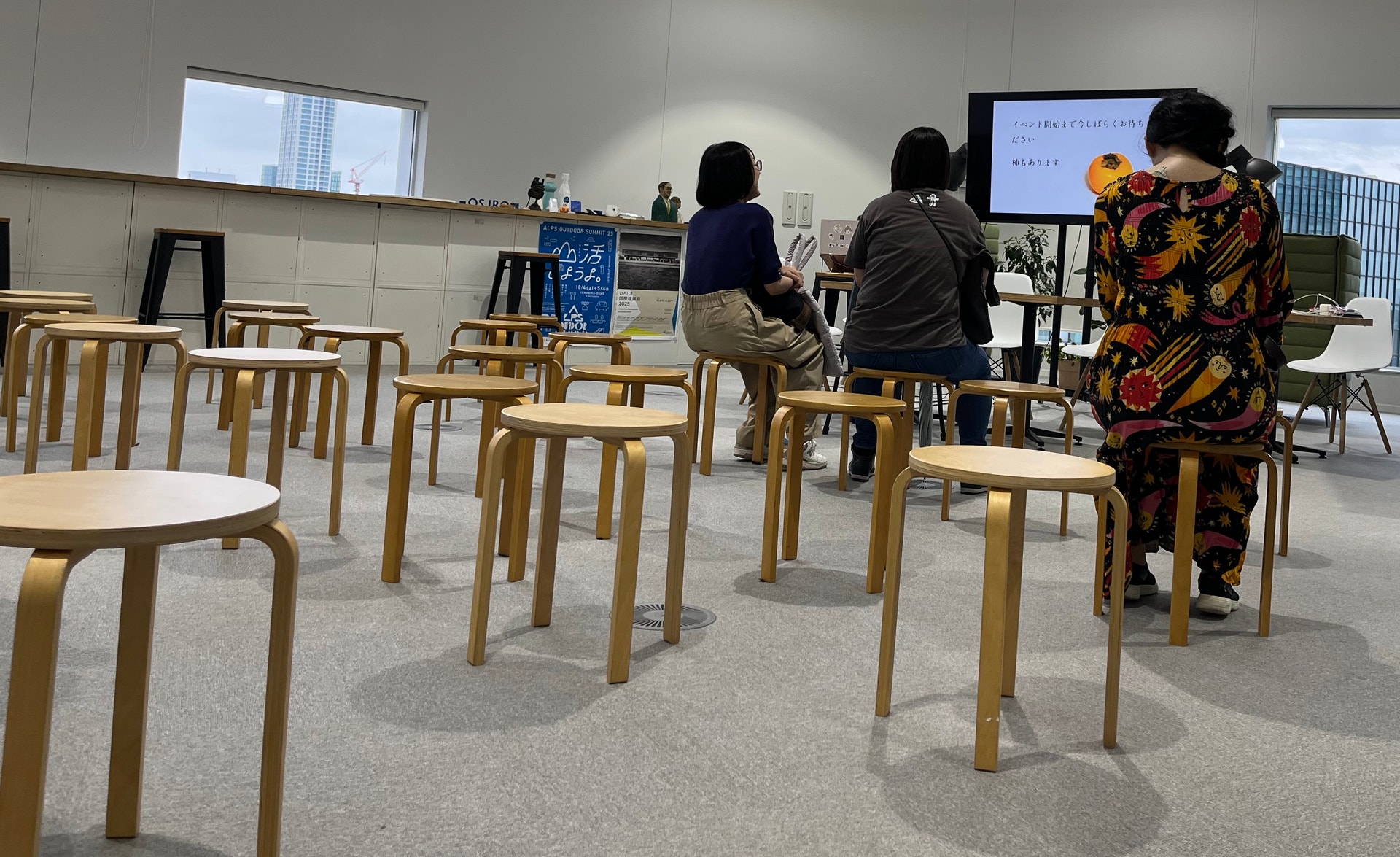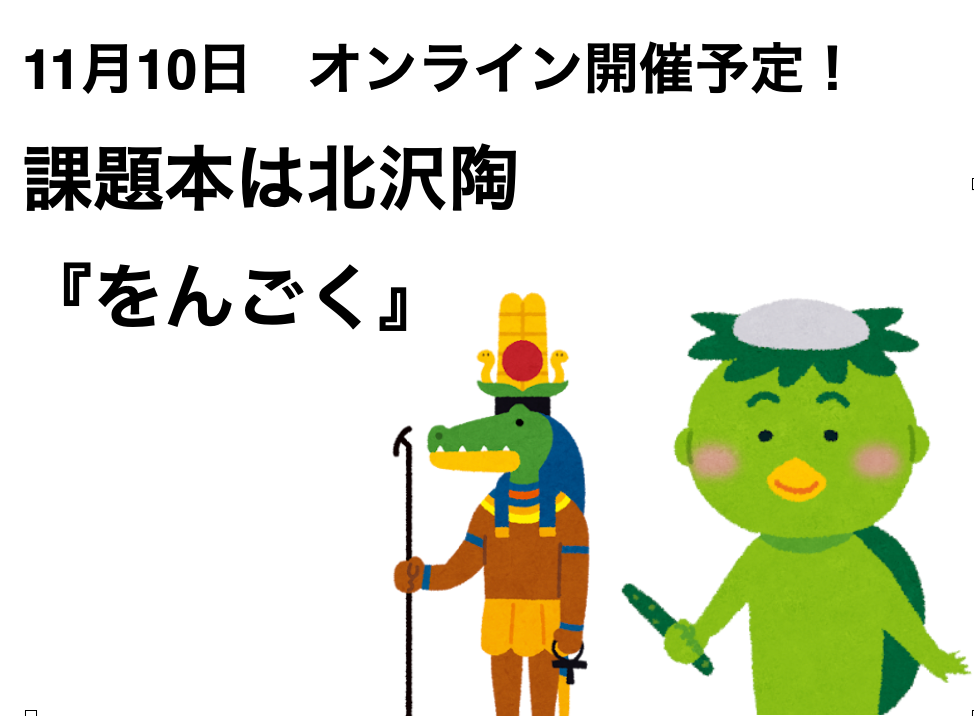開催から少々日が経ってしまいましたが、去る10月4日(土)に猫町倶楽部主催でトークイベント「ホラー小説入門」を開催しました。
読書会コミュニティ「猫町倶楽部」では、様々なテーマで選書された課題本で読書会を開催していますが、これまで取り上げてこなかった「ホラー」をテーマに読書会を開催することとなり、その前哨戦あるいは入門講座ということで本イベントを企画した次第です。
ゲストには、ホラー、怪奇幻想小説の書評でおなじみの朝宮運河さんをお招きし、渋谷のOSHIROスタジオとZoomを用いてオフライン/オンラインのハイブリッド開催しました。
当日の様子、トーク内容をまとめた開催レポートです。
イベント当日はまさにホラー日和な曇天!小雨も降りしきる中、設営サポーターたち(@サヨコ、@カエデ、 @七尾)は会場へ向かいます。主宰のタツヤさん、ほどなく朝宮さんもいらっしゃり、トークセッションの聞き手を担当するサヨコさんとお二人がトークの進行の打ち合わせをしている間に、他のメンバーは椅子を並べたり、柿を飾るなどしながら会場の設営をします。↑皆様をお出迎えした柿のスライド。リアル柿も会場にいました。
開演15分前に受付を開始。開場直後から続々と参加者の皆さんが到着されて、皆さんのテンションの高さも感じられて嬉しい限りです。
↑開場直後の様子。このあと続々と参加者が。
そして定刻通り15:45にイベントをスタート。まずは主宰のタツヤさんからの挨拶です。イベント参加者の約半分の方が一般申し込みということで、猫町倶楽部についても普段より丁寧めに説明がありました。
タツヤさんも挨拶の中でおっしゃっていましたが、猫町倶楽部はあくまで読書会がメインのコミュニティ。ゲスト講師によるトークやレクチャー付きのイベントは開催していますが、必ず参加者同士による読書会も実施しています。今回は馴染みのないホラー小説へのハードルを低くするためまずはトークイベントのみで開催する運びとなりました。
そのおかげでか、ホラーを読んだことのない猫町倶楽部常連のメンバー、逆に猫町倶楽部に参加したことのないホラーファンの方から大勢のお申し込みをいただきました!ありがとうございます😊(もちろん、ホラー大好き猫町メンバーも!いつもありがとうございます!)
これを機にホラー好き、そして猫町倶楽部の読書会に興味を持ってくれる方が1人でも増えることを願うばかりです。
続いて朝宮さんからもご挨拶をいただき、司会から諸々の案内も済んだところでさっそくトークセッションのパートへ。聞き手のサヨコさんへバトンタッチします。
最初に朝宮さんやサヨコさんご自身のホラーにハマったきっかけや原体験などもお話しいただきつつ、ホラー小説の誕生からエンタメのいちジャンルとして育つまで、そして令和のホラートレンドなどを、最近刊行された朝宮さんのホラー小説ブックガイドに掲載された作品を軸にトークいただきました。簡単なトークのまとめと紹介された本の一部を私の主観(+ケッチャム成分トッピング)でお送りいたします!
私たちはなぜホラーを読むのか
そもそも「ホラー小説」とはどのような小説なのでしょう、という問いかけからスタートしました。
朝宮さん著書『現代ホラー小説を知るための100冊』は、ホラー小説を「この世ならざることが起きる」ことを条件として定義し、あくまでホラー小説として分類できる作品を(国内作家に限定して)集めた一冊です。こちらのブックガイドでは焦点をホラー小説に絞って俯瞰することでホラーの輪郭が分かる本。
『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリーまで』では、作中で起きることは必ずしも「この世ならざること」には限らず、リアル路線に寄った作品も多く見受けられます。ホラーだけにくくるにはとどまらず、ミステリやサスペンス、犯罪小説にも分類できそうな、ボーダーライン上にある作品が多いです。
『現代ホラー小説を知るための100冊』を参考にしてホラー小説を定義するなら、一言で言うと「怪異と恐怖の文学」。この世ならざる現象が起きた時に想起される感情によってその作品のジャンルが見えてくるという朝宮さんのお話が非常に興味深かったです。
この世ならざる現象が起きた時に「楽しいという感情が想起されればファンタジー」「現象を分析、解明しだすとミステリー」「恐怖を感じるとホラー」、どこのポイントで読者はアドレナリンが出るのか。
そうなると、あれはホラーなの?これはホラーなの?という疑問がちらほらと。。。
例えばスティーブン・キングの『ミザリー』はホラーではなくサスペンスに近いのでは?作中で起きていることはあまりにも恐ろしいが、ジャック・ケッチャムの『隣の家の少女』も純粋な意味でのホラーではないかも?等々。
スティーブン・キング『ミザリー』
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167705657
ジャック・ケッチャム『隣の家の少女』
https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594025342
脱線しますが、バイオレンスが売りのケッチャム先生。去年扶桑社から刊行された短編集『冬の子』は怪奇幻想な風味漂う作品も多数収録されており、これまでのイメージを一変させる一冊でした。あまりにもグロい話はちょっと…という方には、こちらの一冊をケッチャムデビューにオススメします!(※朝宮さんではなく私が勝手におすすめしています)
ジャック・ケッチャム『冬の子』
https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594098780
ホラー小説はいつ生まれたのか?
さてそんなホラー小説ですがいつ頃生まれたのでしょうか。正確にはホラーの元となったゴシック小説の嚆矢は1764年にイギリスで誕生した「オトラント城奇譚」とのこと。読者の生活とは遠く離れた世界観で幻想的な小説が書かれるようになり、『嵐が丘』や『フランケンシュタイン』と言った文学史上の傑作を生み出したゴシック小説からやがてホラー小説の芽が出て来ます。
メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』(デルトロの映画も楽しみですねぇ)
https://www.shinchosha.co.jp/book/218651/
日本産ホラー小説の誕生
明治以降、江戸川乱歩ら日本の作家たちもポーの影響でホラー小説を書くようになります。そして日本にはもう一つ、怪談という文化がありました。もともと人々の口を通して語られていた怪談が文学として発展し、怪談作家の岡本綺堂が登場します。岡本綺堂のような伝統的な怪談をベースとした作風と、西洋由来の恐怖を論理的に構築する乱歩の系譜、ふたつの異なる気質のものがミルフィーユのように重なりながら日本のホラー小説は発展していきます。
岡本綺堂『白髪鬼』
https://amzn.asia/d/0FKL5DX
現代では、西洋から来たホラーの系譜が現在の作家を席巻していそうですが、現役作家にも岡本綺堂の影響が色濃い作家は活躍しており、特に宮部みゆきの怪談ものなどその色合いを強く感じます。あとサヨコさんが「首ざぶとん」を異様な熱量で推していましたことを報告しておきます。
エンタメとしての現代ホラー小説
いよいよ91年に鈴木光司「リング」が登場。VHSによって呪いが広がる、何の縁もゆかりも因果もない人が無作為に死ぬ展開は新たな恐怖表現の手法になりました。93年には角川ホラー文庫が登場し、非常に彩り豊かな恐怖が書かれホラーはエンタメのいちジャンルとして世に定着しました。
今、そしてこれからのホラーとは?
そして作り手が読者をさらに怖がらせようと手法を突き詰めていった結果、現代ではモキュメンタリーがホラー小説界をも席巻しています。モキュメンタリーは映像作品の影響も強いとは思いますが。そういえば他メディアからの影響も受けながら変化していくのもホラーの特徴ですね。今回は小説に絞ってお話しいただきましたが、ホラーの変遷にはネット文化の影響も絶大です。
そして現代ホラーは90年代のエンタメ路線とはまた違う、より読者のリアルな生活と地続きの恐怖、より生っぽさがトレンドになっています。その集大成とも呼べる作品が背筋『近畿地方のある場所について』。
人気作家の名前が背筋、梨、雨穴等々ちょっとハンドルネームらしいのも今風…。
ところでこの90年代から2000年代へ至る変遷を見ていると、小野不由美の「屍鬼」から「残穢」への変化はまさにその時代の恐怖のトレンドの最前線を突っ走っていたのだなー!すげーー!と大興奮ですね!
ではこれからの恐怖のトレンドは?という話に。「リミナルスペース」なる概念が注目を集めているとのことです。静かな怖さ、少し幻想的な雰囲気もまといつつ皆で恐怖の感覚を共有できるあたりが今時だな~と感じました。また、明確な対象や実在する属性などが恐怖の対象とするわけではないので、差別に結びつけにくいという点もいまの時代の空気として受け入れられやすいのではというお話もとても納得です。リミナルスペースを解説した書籍がフィルムアート社から刊行され、発売直後からホラー小説好きの方々も話題にしていました。
読書会で恐怖を語り合おう
社会が安定しているとホラーが流行る(太平洋戦争の頃はホラーなんて書ける雰囲気ではなかったでしょう…)という意見もありますが、逆に社会不安によってホラーを求めることもきっとあるのではないでしょうか。あの時私たちは何に怯えていたのか、それは何年も経ってから俯瞰で見られるようになってから見えてくるのかもしれません。
読み手は作品内の恐怖表現に怯えながら、人間の悲しみや理不尽さが吐き出されたホラーにある種の誠実さを感じて慰めや癒しにつながることもあり得ます。
もしかするとホラー小説は、人間はなぜ生きているのか、世の中はなぜこうなのか、薄っすらと教えてくれるジャンルかもしれないと朝宮さんの談。
読書会で、この小説の怖さの根源は何なのか、わたしは何が怖いのか、各々が怖さを語り合うことが自己開示にもつながり、新たな読書体験にも期待できそうです。
トークセッションの約1時間はあっという間に過ぎて、最後に参加者からの質疑応答の時間。
オフライン、オンライン両方から次々と質問が。中にはホラーが苦手になった原体験を語りつつ、そんな自分にも読めそうなホラー小説を教えてください、という勇気ある質問も!そもそもホラーが苦手なのに参加してくださったことに感謝です。
質疑応答も途切れることなく質問をいただき、答えきれない質問もある中、時間が来たので終了です。
あっという間の90分でした。この短い時間の中でホラー小説の歴史を知るとともに、作品もたくさん紹介いただきました。入門編と銘打ったイベントでしたが、ホラーの歴史が立体的に見えて来てマニアの方々にも非常に楽しんでいただけたのではないでしょうか。今回のイベントをきっかけに、自分にはこんなテーマのホラーが合うのではないかなどなど、ご自身にあった作品や作家を見つけてください。トーク中に紹介した中でも気になった作品はぜひお読みいただきたいと思います。
ブログに書ききれないほど、当日のトークでは朝宮さんからホラーの奥深い世界、魅力的な作品を語っていただきました。ホラー小説をもっと知りたいという方はぜひ朝宮さんのブックガイドを手にとって、色々読んでみてください!
トークイベント後は、希望者で懇親会へ。もちろん朝宮さんにもご参加いただき、ホラーファンとの和気藹々とした交流がとても楽しかったです。
さて、冒頭で書いた通り、猫町倶楽部は本来は読書会を行うコミュニティです。今回はホラー小説の入門編ということでトークイベントを開催しましたが、11月からはホラー小説を読み、感想を語り合うホラー小説読書会を開催します。
朝宮運河の”このホラー小説を読め!”第一回 北沢陶『をんごく』
まるで『をんごく』のマスコットキャラがワニと河童みたいだ…
ちなみにワニとか河童とか気になる方はぜひ朝宮さんのXのアカウントをご覧に。。。。
https://x.com/unga_asamiya?s=21&t=j0jnkw4-e_mLglm9KMClhA
本イベントは毎月開催、全6回シリーズで課題本は朝宮さんに選書いただきます。
第一回は11月10日(月)、課題本は北沢陶「をんごく」です。第一回は朝宮さんもゲスト参加予定です。
ただいま参加申し込み絶賛受付中です。下記イベントページよりぜひ申し込みをお願いいたします。
https://nekomachi-club.com/events/7f2bf1f32bd1
長くなりましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました。また、本イベントへご参加くださった皆様、朝宮さんにも改めて御礼申し上げます。
またぜひ読書会でお会いしましょう!