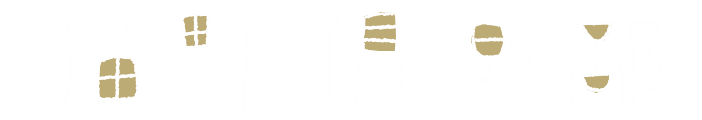一話ごとの題が長いが、本文を読む前になぜか引き込まれた。
読んでみると、日常の何でもない、隣近所か、同僚か、友人にでも聞いたような、どこにでもありそうな話が溢れている。ときには不思議な話、ありえないような話、息抜きのような話もある。話ごとの強弱を感じた。
視点がころころ変わり、時間が飛ぶので読みにくいはずなのだが、面白い。
誰でも一度くらい「自分の人生は、自分の存在は意味があるのか」と考えたことがあるはず。やりがいのある仕事だとか、かけがえのない家族だとか、自分しかできない、自分の存在でしか成しえない、何か特別なものがあるだろうか、と。いい大人になってからも、私は考えた。突き詰めてみたけど何も結論は出ないし、特別な存在ではない、と思い知らされる。そして、淡々と人生は続いていく。意味があろうがなかろうが、死ぬまで続いていく。
読書会後「自分の記憶や体験は、100年も経てば誰にも話されずに忘れられていく。でもそこに意味がないわけではなく、何かがあったということである。それは教科書に残るようなことと同じ意味がある」と著者は言った。
名のある研究者や作家、音楽家など、ネットで検索してすぐに名前が出てくるよう人物以外の大勢の人。私もその一人だ。そんな人の人生にも確かに何かがあって、意味がある。ああ、そうなのか。この本の著者自身がその思いを込めて書いたと知ったとき、すとんと落ちた。この本に惹きつけられたのは、そこだったのか、と。

2021/07/09 00:23